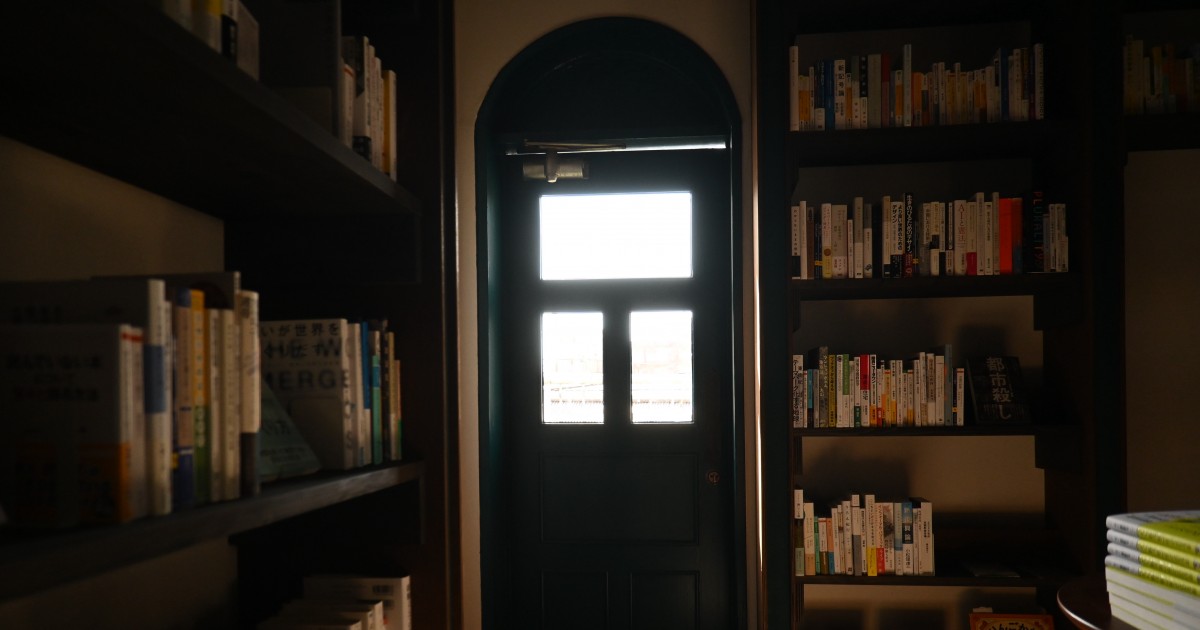エッセイの哲学、青葉市子記念本、ジェイコブズ
気づけばお店をオープンして1ヶ月半ほどが経った。通常の書店+喫茶・喫酒の営業はある程度慣れてきて、より充実した内容にしていくためにどんな工夫を凝らそうかという試行錯誤へと気持ちが向かってきているし、特集棚やTALK LIVE、場所貸しなども一通り執り行うことができ、少しずつだけど手応えも感じてきている。コワーキングや貸し棚、ネット販売や古本など、まだまだ最低限整備しなければいけないことはたくさんあるし、何よりこのbookpondという場を面白くするためにはまだまだ足りないピースがたくさんあるのだけれど、とはいえようやく日常的に本を読んだりする生活が取り戻されつつある。
けれども、なんというかここ半年くらいあまりにバタバタしすぎていて、腰を落ち着けてじっくりと勉強したり、作品や事物に触れたり、ものを考えたり、といった基礎体力が落ちてしまっているような気もして、そうしたケの勉強や思考のリズムを取り戻す意味でも、できるだけ毎週このニュースレターを更新していこうかなと思い立った。
今日は日曜日で通常であればお店の営業なのだけれど、ここ数年縁あってたびたび訪ねている群馬県の前橋付近で外せない予定が入り、お店は休みにして、横浜から高崎まで湘南新宿ラインでゆったりと向かっている、そんな旅路での一筆書き。
さて、なにを書こうかと思い立ったとき、8/23に行ったbookpond初のTALK LIVEについては振り返っておかなきゃいけないと思い至る。僕が最も信頼・尊敬する同世代の書き手の一人であるエッセイスト・生湯葉シホさんと、面識はないけれど『僕たちは言葉について何も知らない:孤独、誤解、もどかしさの言語学』『井筒俊彦 世界と対話する哲学』といったご著書を拝読して対談相手として直観的に名前が浮かんだ哲学者・小野純一さん。いちおう問題設定はしたものの、正直どのようなかたちでトークが展開するのかはかなり未知数で、ライヴというよりはジャムセッションに近い企画ではあったが、結果としてとても素晴らしい場となった。「読書の呪術的作用」という問いに対して、小野さんと生湯葉さんによる静かな、でもとめどない掛け合いの中で少しずつ接近していく、緊張感と穏やかさの同居する心地よい時間。言語哲学者とエッセイストによる「エッセイの哲学」が立ち上がったようにも思えた。
生湯葉さんはトークの中で「エッセイを書く際、読者の共感を得やすいように解像度をあえて落とす、といった戦略的な書き方はあまり意識していない。本当に、執拗なまでに記憶していることを、そのまま書いているという感覚。自分が感じたことを無邪気に並べているだけ」と語った。そして小野さんは生湯葉さんのエッセイを一文一文丁寧にひもときながら、それを読む体験から引き起こされる作用を「忘れ去っていた記憶、あるいは当時なかったことにしていた事柄が、鮮明に呼び起こされた感覚」と表現した。
これは単に他者の感情や経験を自分に引き付けて理解する「共感」とは異なる。むしろ、小野さんがトークの終盤で「それまで知らなかった語彙や視点に触れ、それが自分にはなかったものだとハッとした時な、つまり言葉を与えられたとき、世界の見方がそこだけ明確になる──これは因果関係のない、呪術的な効果」と指摘したように、むしろ自分が拡張される経験だといえる。
そしてそうした「拡張」が、エッセイというきわめて個人的な記述から引き起こされている点がとても面白いと思った。小野さんも「独自でありながら他者と共有され、読む人それぞれが違う事柄を思い浮かべる」というエッセイの興味深さを指摘していたけれど、生湯葉さんの紡ぐ文章には、読み手それぞれの個人的な経験や感情──しかもそれまでは意識の遡上にのぼっていなかった経験や感情を湧き出させる力がある。これこそがエッセイを読むことの醍醐味であり、ひいては「読書」そのものの醍醐味にも通ずるのではないかと、じぶんが本を読んだりつくったり売ったりすることの意味というか、コンパスのようなものをいただいたTALK LIVEとなった。
「読書」「エッセイ」についての哲学的・実践的考察として、かなり深いところまで迫った議論になったと思う。『僕たちは言葉について何も知らない』『音を立ててゆで卵を割れなかった』を読んだ方はもちろん、未読の方でも十分にお楽しみいただけるので、気になった方はぜひ下記よりアーカイヴ動画を購入してほしい。
サクッと書くつもりが、思いのほか長くなってしまった。最後に、最近読んだり観たりしてよかったものをつらつらと。
まずちょっと変わり種なのだけれど、『ICHIKO AOBA 15th Anniversary Book』。青葉市子さんの活動15周年を記念し、2025年1月に京都と東京で開催されたコンサートの密着ドキュメント。舞台裏や各公演のレポート、公演直後のインタビューまでを取材した記念本なのだけれど、BASEで一般販売もされている。僕は青葉さんはちょくちょく聴くもののそこまで熱心なリスナーというわけではなかったのだけれど、レポートの書き手が、大好きな書き手である橋本倫史さん(bookpondでも著作はだいたい揃えています)だと知り即購入。青葉市子という人間の魅力はもちろんなのだが、何より橋本さんのテキストを読むと救われた。控えめで、でも熱情と温かみのある地の文。そして、丁寧に紡がれた会話文。「取材して、書く」という営みに関して、とりわけ40前後の書き手で右に出る人はなかなかいない方だと思う。読了後すぐ青葉さんのWebサイトから少々暑苦しいメールをお送りし、さっそく仕入れも完了した。なかなか書店では出会えないレア物だと思うので、ぜひお買い求めに来てほしい。
成馬零一『坂元裕二論:未来を生きる私たちへの手紙』も、期待通り楽しく読んだ。坂元裕二の系譜を丁寧にまとめた本としての価値はもちろん、「他者との対話」「手紙」といったコンセプトも納得感があるし、何より本書で紹介される固有名詞に触れているだけで幸福だった。坂元裕二が好きな人は必読。他者とのコミュニケーションの本来的な不可能性の中で、それでも少しずつ他者を手繰っていくことの豊かさこそが坂元裕二の最大の魅力だと僕は思っているのだけれど、その感覚が成馬さんの丁寧かつ解像度の高い言葉で整理された感覚もあった。
その他にも、沖俊彦『クラフトビール入門』も面白かった。昨今のクラフトビールブームの起源たるアメリカのクラフトビールは、カウンターカルチャー、DIYとしての側面が強かった。他方、地ビールの前史がありつつ欧米の輸入である日本のクラフトビールは、そもそもホームブリュワリーが法的に禁じられているという制約もあり、そうしたDIY精神は薄く、すぐに大手も参入。ちょっと大げさかもしれないけれど、そのダイナミズムは戦後民主主義の受容ともなんとなく重なって見えたし、その「軽薄さ」のようなものからこそ生まれてくるものもあるとは思っていて、そういう視点からもクラフトビールをもっと勉強してみたくなった。
それから今月の特集「都市とアジール」にあわせて、都市論系の本を意識的に読んでいる。まずは「読んだふり」をしてきた古典をということで、ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』にざっと目を通してみた。再開発批判の古典。都市の多様性を生み出す「4つの条件」──①機能の複数性②街区の短さ③古い建物の混在④十分な人口密度──というアイデアを、学術的な正当性や分析の根拠の希薄さはともかく、提示したことには大きな意味があると思うし、いまでも繰り返される再開発批判のテンプレートは(「なんかそんな感じがする」という印象批評的なものも含めて)すでにこの時点である程度出来上がっているのだと思った。そして山形浩生の解説はさすがで、1950年代ニューヨークの劣悪な住環境に対する処方箋としての都市計画、そしてそのさらなるオルタナティブとしての本書があったという点はシンプルに勉強になった。
すでに登録済みの方は こちら